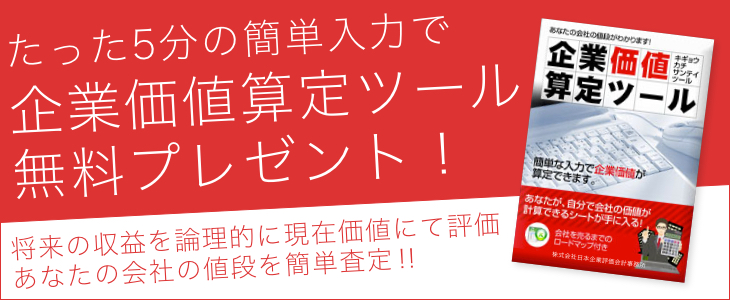M&Aは買い手側からすると、既存事業の拡大や新規事業への進出などのメリットが多くありますが、当然にお金が必要になります。
先立つものがなければ、M&Aをしようと思ってもできません。かと言って、手元に資金がないといった状況の会社様が大半かと思います。こでは、M&Aの実行のためにどのような資金調達手段があるのかを紹介したいと思います。
M&Aのための資金調達方法
資金調達方法は、法人を前提にお話しすると、実に多様な手段があります。まず手元の資金すなわち自己資金がすでにあれば、全く問題ないですね(当たり前です)。自己資金が潤沢にある会社であれば、以下は読む必要がないと思います。自己資金がない場合、ファイナンスをすることになります。ファイナンスの手法としては、増資による新株発行、借入金ほか社債や転換社債、あるいは借入金と言っても、準資本的性格のある劣後ローンなどがあります。大まかにまとめると以下のようになります。
| 形態 | 分類 | リターン | 満期 | 議決権 | デフォルト回収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式(エクイティ) | 普通株式 | 配当 | 無 | 無 | デットとメザニンおよび優先株式の配当を行った後の残余財産のみ |
| メザニン | 優先株式 | 優先配当 | 通常無 | 通常無 | デットとメザニンの配当を行った後の残余財産のみ |
| 優先出資証券 | 通常無 | 通常無 | |||
| 劣後債 | 劣後利払 | 有 | 有 | デットの返済を行った後の残余財産のみ | |
| 劣後ローン | |||||
| 転換社債 | 利払、株式への転換、配当 | 有(転換したら無) | 有(転換したら無) | 転換前は負デットと同等、転換後はエクイティと同等 | |
| デット(負債) | 普通社債 | 優先利払 | 有 | 無 | 優先的に分配 |
| 貸付金 | 優先的に分配(担保がある場合は、最優先) |
手元資金
手元資金、すなわち自己資金でM&Aを実行する場合、余剰資金の活用ということで資本効率を高めることにもなりますし、会社の財務内容の悪化ももたらさない(M&Aが失敗すれば別ですが)ため、最も望ましい方法です。もちろん、自己資金があるなら困らないよ、と言われてしまいそうですが。
新株の発行

新株の発行というのは、いわゆる増資です。調達した資金は返済の義務がなく、会社の資本金に組み入れられるため、長期的な視野に立って利用できる資金であると言えましょう。また上場企業であれば、既存の事業の利益率が下がってきている中で、株式により調達資金を有効活用すれば、自己資本利益率が向上するため、株価上昇が見込めることとなります。一方で、株式により調達した資金は返済義務がなく、また利払いも義務ではないのですが、株主は当然に配当を求めることになります。配当金は法人税を支払った後の税引き後当期純利益から支払うこととなりますので、支払利息が税務上の損金となる借入金よりも、結果的には資本にかかるコストが大きくなることもあります。もちろん、配当金は利益が出なければ支払えないですし、また支払わないことで何かの問題が生じることはありません。したがって、企業収益に関するリスクは中立的(配当支払いは利益があった時だけなので、利益が出なければ配当支払いもない)であると言えましょう。
なお、当然なのですが、新株の発行は既存の株主の株式持分比率を下げることになります。これによって、それまでオーナーが株主総会でなんでも決定できたのに、外部の株主の意見も聞かなければならなくなるわけですし、場合によっては取締役を派遣されることもあります。また、外部株主が多くなることで、株主総会の開催手続の煩雑化や情報開示など、様々な事務負担が増えるといったデメリットもあります。
負債による調達
負債として調達する手法として代表的なものは銀行から借入をすることです。また、社債という有価証券を発行する方法も考えられます。借入金と社債では、調達の手続がかなり異なってはおりますが、返済義務があり、また返済までの期間が決まっている、という本質的な特徴の部分は同じです。さらに、借入金の場合は期間に応じて利息も発生しますが、これは株式を発行した場合の配当と違って、利益が出て出なくても必ず支払わなくてはいけません。したがって、負債は企業収益が出るかでないかという意味において、会社経営にとってはリスクとなります。もちろん、リスクと言ってもデメリットだけではありません。企業が利益を多額に計上したとしても、支払う利息は一定なので、儲ければ儲けるほど利息の費用負担割合は減っていきます。少ない費用で大きな利益を上げることができるのです。負債比率が高い企業は一般には財務内容が悪い企業と言えるのですが、少ない資本金であっても、借入で資金調達を行って事業を成功させれば、相対的に株主に残る利益は多くなるので、レバレッジ(テコ)が利いた企業ともいえるのです。
また、負債の調達に伴って発生する利息は、税務上、企業の所得から損金として控除されるため、株式の配当金と違って負債の利息は節税効果があることになります。
メザニン・ファイナンスによる調達

メザニンという言葉はあまり聞きなれない言葉かと思います。英語で「中二階」という意味になりますが、ファイナンスの世界では、株式と負債の中間という意味でつかわれる用語であり、株式と負債のいいとこ取りをしたファイナンスの手段です。
メザニンファイナンスは、一般的には、シニアファイナンスと呼ばれる借入や社債よりも返済の順位が低い、すなわちシニアファイナンスが完済された後でしか元本の回収が図れないという特徴を持つため、シニアに比べて資金の出し手にとっては、当然リスクが高くなります。しかしながら、金利がシニアより高く設定されたり、またはエクイティのメリットであるキャピタルゲインも得られるような権利を付与したりすることで、投資家の多様なニーズにこたえる設計が可能となります。米国では以前より普及しておりましたが、日本においても近年の金融の高度化に伴う多様な資金供給手段の一つとして利用が進んできたところです。
メザニンファイナンスの代表的な手法は、劣後ローン、優先株式、転換社債などです。
劣後ローンとは、シニアローン(通常の負債)が完済された後において、返済原資が残ってい場合に限り返済がされ(資本金よりは優先します)、また借入の期間も長いのが一般的で、調達側にとって有利な資金調達手段ですが、金利はリスクが高くなっている代わりにかなり高めに設定されている借入のことです。昨今では公的金融機関が積極的に資金供給していますね。
優先株式とは、一般的なタイプにおいては、株主総会における議決権が付与されない代わりに配当金が多く支払われる、といった設計がなされています。これにより株主総会での議決権を維持したまま、返済義務のないエクイティを調達できるというメリットがあります。
転換社債とは、株式への転換の権利が付与された社債です。発行当初は普通社債としての性質を持っているため、その資金については返済義務があり、また利息の支払いも義務です。しかしながら、社債の元本部分について一定の条件の下、株式に転換できる権利が付与されているため、社債の返済をしないまま、資金が資本金に転換されることがあります。投資家としては、会社の収益が向上してきた時は株式に転換してキャピタルゲインも狙うことができますし、会社の業績が思ったより伸びなければ社債権者として元本の回収が図れますので、リスクとリターンの両面でいいとこ取りをしたファイナンス手法です。上場会社などでもかなり頻繁に利用されている手法です。
以上のように、メザニンファイナンスは、デットとエクイティのいいところを組み合わせた商品と言えますが、どうしてもわかりにくい商品であり、その設計には専門的知識が要求されるとともに、手続きが非常に煩雑となります。また、株式なのか負債なのかの定義が複雑であるため、当然に税務上の取り扱いも複雑になっています。
資金調達の最適化
これまでお話ししたように資金調達についてはかなり多様化しており、様々な手段が開発されてきました。しかしながら、株式なのか負債なのか、はたまたメザニンなのかというのは、どれか一つを採用すればいいというものではありません。適切な手法と比率で資金を調達しないと、会社全体の資本構成の均衡が崩れ、様々な問題点が出てきます。株式だけで多額に調達してしまうと、あまりの多数の株主の対応に苦慮したり、負債が多額になってくると、バブルが崩壊した直後の日本企業がそうであったように資金繰りを圧迫して会社自体の破たんのリスクが高くなってきます。したがって、資金調達においては、会社の状況や経済環境に合わせて、適切なプランを練ることが必須であり、その際は専門家の知識を十分に活用すべきなのです。
当社では、銀行や証券の経験者もいるため、経営者の皆様の資金調達に必ずお役に立つことができると思います。詳細をお聞きしたい場合は、一度当社までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。03-6821-4016受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ資金調達をしなくてもできるM&A
別のコラムで、M&Aのための資金調達をお話ししましたが、実は資金調達を行わなくてもM&Aが実行できる場合があるのです。
お金がなくても会社を買えるの?と聞かれれば、可能です、と回答できるのです。
合併
M&Aは何も対象会社の株式を現金で買い取ることだけを指すのではありません。合併という主要なM&Aの手法は、基本的には自己資金がなくてもできるM&Aの手法です。
ただし、合併の際には、吸収合併であれば存続会社(買い手)が自社の株式を消滅会社(売り手)の株主に交付することになりますので、企業価値によっては、売り手の株主が買い手の大株主になってしまい、どちらが買い手だったのかわからなくなることもありますが。
株式交換

合併に似た手続きですが、合併は複数の会社が一つの会社になるという手続きである一方、株式交換は基本的には、売り手企業が買い手企業の子会社になる、という点で大きく違います。株主構成を別にすれば、買い手企業の経営陣が売り手企業を子会社として経営していくことになりますので、合併と違って同一の会社になるわけでなく、そこには支配―被支配の関係が存続することになります。
やや専門的ですが、株式交換を法的に説明すると、株式会社(売り手側)がその発行済株式の全部を他の株式会社(買い手側)に取得させることであり、対価として買い手企業自体の株式が売り手側企業の株式に交付することになるわけです。
やや専門的ですが、株式交換を法的に説明すると、株式会社(売り手側)がその発行済株式の全部を他の株式会社(買い手側)に取得させることであり、対価として買い手企業自体の株式が売り手側企業の株式に交付することになるわけです。
ただし、売り手側企業の株主にとっては、M&Aの対価として現金ではなく、株式が入ってくることになりますので、手に入れた株式が換金できない場合などは売り手から了解を得ることができない場合があります。したがって、株式交換は未公開企業ではなく、交付される株式が市場で簡単に売却できる上場企業が主に利用しているM&Aの手法と言えるでしょう。もちろん、売り手が未公開株であってもM&Aの対価として了解してくれるのであれば、未公開企業であっても株式交換によるM&Aを実施することは可能です。
LBO(レバレッジドバイアウト)
レバレッジドバイアウトとは、買い手が売り手の企業の資産を担保にして、借入を行い、その資金で売り手企業を買収する手法です。他社の資産を担保に入れて資金調達するので、実質的には負債により資金調達をしているのですが、自社の与信力がなく、自社単体では借入ができないといった状況であっても、場合によってはLBOのスキームで資金調達ができることがあるのです。常識的に考えると、他人の資産を担保に入れてお金を借りるなんてひどい話なんですが、買収が完了した後は、子会社の資産を担保に親会社が借入をしているといった形になるため、特段おかしな状態にはならないわけです。順番を逆に考えると、担保価値のある子会社の資産を担保に入れてお金を借り入れるなんて言うのは、よくあることですが、LBOはこの順番を逆にした手法なんですね。もちろん、借入資金は返済しなければならないので、LBOスキームで買収をする会社は、資産価値が十分にあるか、あるいは将来的な返済原資となるキャッシュフローが潤沢な企業にしか適用できません。
当社では、有望なM&A相手を見つけたにもかかわらず、M&Aのための資金がなくてM&Aが実行できない会社様に対して、上記のようなスキームを提案してM&Aを遂行できるためのコンサルティングを提供しております。詳細をお聞きしたい場合は、ぜひ一度当社までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。03-6821-4016受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ